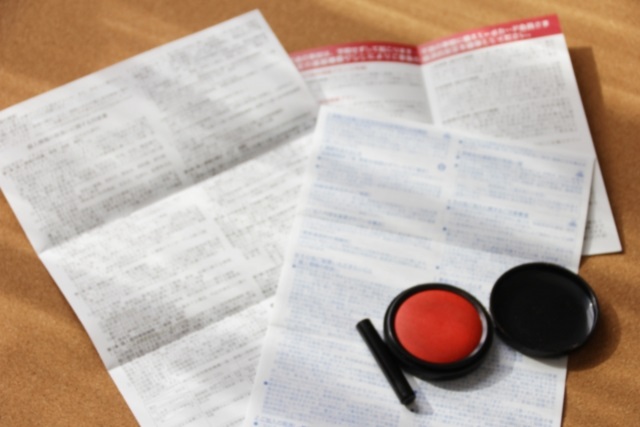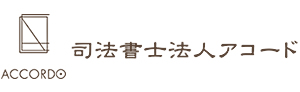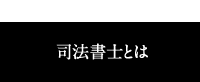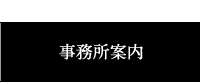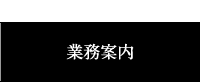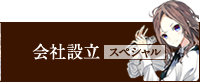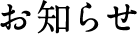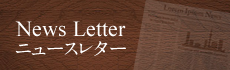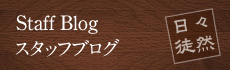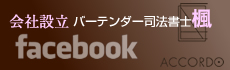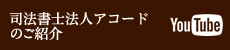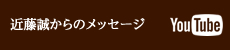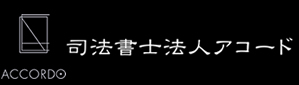【民法改正】保証について
- 2018-01-30
-

「絶対的に迷惑はかけません」「名前を借りるだけです」などと言われ、知人の保証人になって人生が破綻するようなドラマや映画を観たことはありませんか?
今回の民法改正では、保証人の保護を図るために新設されたルールがあります。
経営者等(取締役,大株主等)以外の者が、事業資金を主債務として保証する場合、その保証契約締結の日前1ケ月以内に、保証人になろうとする者が公証役場に出向き、公正証書によって保証する意思表示を明確にしなければ無効となります。
*保証人の意思確認を公正証書によりすることで、安易な保証契約の締結を防止するために新設される条文です。
ただし,保証人になろうとする者が次に掲げるものである保証契約については,公正証書は不要となります。
・主たる債務者が法人である場合の、その理事・取締役・執行役又はこれらに準ずる者
・主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する者等
・主たる債務者(法人を除く)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
*保証人の保護を図る一方で,全てのケースに公正証書作成を義務付けると、中小事業者が金融機関から融資を受けづらくなってしまいます。
「事業の状況を把握しやすい者が保証人になるなら厳格な手続きじゃなくてもいいですよ」という適用除外の本条が設けられています。
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
・財産及び収支の状況
・主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
・主たる債務の担保としてほかに提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
上記の内容を主債務者が提供せず、又は事実と異なる情報を提供したことにより保証しようとする者が誤認し、債権者がそのことを知りながら又は知ることができたにもかかわらず、保証人(法人を除く)が保証契約の申込みや承諾の意思表示をした場合は、保証人は保証契約を取り消すことができる。
*保証人に対し,契約前の保護と共に,契約締結後でも一定の場合は取り消しできることを規定し,債権者との利益調整を図る条文です。