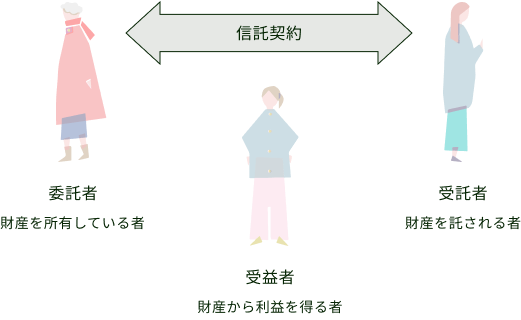活用事例① 認知症対策として
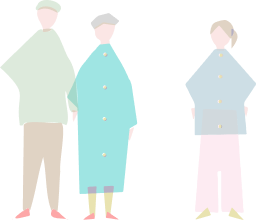
事例ペルソナ
- 高齢の夫婦と一人娘
-
父親の資産は下記のとおり
・自宅
・賃貸マンション
・預貯金3000万円 - 父親の認知症が不安
- なるべく成年後見は利用したくない
多くの家庭では、不動産や預貯金などの財産は稼ぎ手であった父親名義になっていると思います。もし父親が認知症になったことで、家族のために自由に財産が使えなくなってしまったらどうでしょうか?
生活費のための預金引き出し、アパートの修繕や賃貸借契約、バリアフリーのマンションへの住み替え、施設入所費支払いのための定期預金の解約等はいったい誰がどんな権限で行うのでしょうか?
何も対策をしていなければ、成年後見制度を利用するほかありません。会ったこともない専門職が成年後見人として選任され、お金の使い方について生涯ずっと家庭裁判所の監督を受けていかなければならないのです。
この事例では、娘さんが受託者となって家族信託を利用することになりました。娘さんは受託者として、自分の判断で財産の管理・運用をし、必要があれば賃貸マンションを売却することも出来ます。
家族の財産は、強い信頼関係で結ばれた家族が守り承継していくという当たり前のことに、法律上の根拠を与えていくことこそが、家族信託の目的であるといってよいでしょう。
活用事例② 事業承継対策として
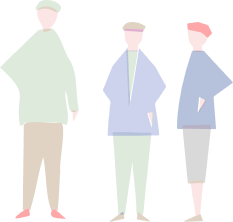
事例ペルソナ
- 高齢の父親は会社を経営している
- 長男が会社を手伝っているが、まだ経験不足
- 次男とは仲が悪く、普段付き合いはない
- 会社の株式は父親が100%所有し、取締役は父親のみ
多くの中小企業では、社長ひとりが経営者兼オーナーであることが多いと思います。ではもし、社長が認知症になってしまったり急死したら、会社はいったいどうなるのでしょうか?
社長を失った会社は一切の経営判断をすることができずにストップします。後継の経営者を選ぶためには株主総会を開くことになりますが、社長は株主でもあるわけですから株主総会は開催できません。
代表者である社長がいなければ、契約をしたり取引を継続することは出来ません。大事なお客様との取引関係、従業員の雇用、借り入れの返済はいったいどうなってしまうのでしょうか?事業承継の道筋を立てておくことは経営者として重要な仕事であるといってよいと思います。
この事例では、長男に株式を信託することで対策を講じました。株主総会での議決権は受託者である長男が行使することになりますが、父親が元気なうちは長男に議決権の行使内容を指図してコントロールすることも可能です。
活用事例③ 共有不動産対策として
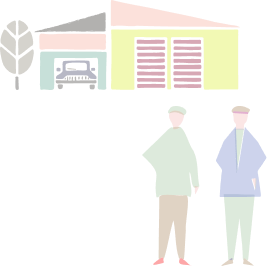
事例ペルソナ
- 高齢の兄弟が不動産を共有している
- いずれば売却するしかない
- 共有者の一人が病気や認知症になったら?
- 共有者が亡くなれば、相続によって共有者が増える
すでにご高齢の兄弟が不動産を共有しているケースは少なくありません。しかし、共有の不動産を売却するためには、共有者全員の合意が必要となります。
「俺は協力しない」「あの土地はまだ値段が上がるはずだ」「先祖代々の土地を処分するなんて納得できない」などど、共有者のうちの一人でも反対すれば売却することは出来ませんし、共有者の誰かが認知症になったり、行方不明になってしまったような場合には完全に「塩漬け物件」になってしまいます。塩漬けになっている間に共有者が亡くなれば相続によって、さらに多くの共有者が出現することになります。
この事例では、共有者である兄弟全員が長男の息子に不動産を信託しました。長男の息子は、受託者として兄弟に代わって管理をしたり、場合によっては自分の判断で不動産を売却することができます。